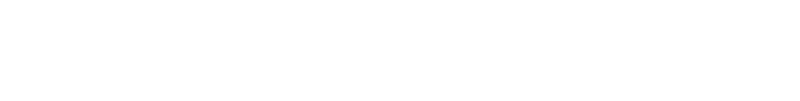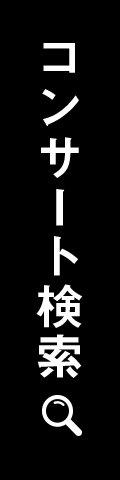特級グランド・コンチェルト直前インタビューVol.2 北村明日人さん

「モーツァルト 第23番」

聞き手:桒田萌(ライター)
特級グランド・コンチェルト直前インタビュー、第2弾は北村明日人さん。第1弾の桑原志織さんとは、東京芸術大学付属高校時代の同門の先輩・後輩です(伊藤恵先生門下、桑原さんが1年先輩)。全国各地のステップアドバイスやレッスン、各楽器の伴奏者としても引っ張りだこの北村さんに、グランプリ受賞後の活動と、今回のモーツァルトのピアノ協奏曲について語っていただきました。
ベートーヴェンに多くのレパートリーを持つ北村さん。近年、演奏されることの増えてきたモーツァルトのピアノ協奏曲を演奏されます。改めて、北村さんの持つモーツァルトへの印象を教えてください。
年を重ねるごとに、モーツァルトの音楽に出てくるような単純なスケールの音型がおもしろくなってきています。音が上行しているだけで、モーツァルトがいかに喜びを感じていのか。そんなことがわかるようになってきました。
もともと、僕の中でモーツァルトはとっつきにくい存在でした。特に学生時代は、自分が得意としていたベートーヴェンと同じような取り組み方をしていたこともあり、自分自身がモーツァルトの作品に覆い被さってしまうような弾き方になってしまっていて。
でも、年を重ねるごとにだんだんと冷静に弾けるようになってからは、モーツァルト作品への見方が変わりました。たとえば、作品における一つひとつの音が、どんな重さで、どんな場所に位置して、どんな方向に向かっていくのかが見えてくるようになった。その音が、どんな理由でそこに存在しているのかがわかるようになったというか。
確かに、ベートーヴェンとモーツァルトでは、音の出し方がまったく異なるように思います。
そうなんです。ベートーヴェンの音楽は、自分の声で喋りたくて仕方ないといった雰囲気があるので、僕も積極的かつ能動的に演奏します。一方でモーツァルトは、演奏者が声を大にしなくとも十分。個人的には、できるだけ自分が「無」の状態で弾けるのがベストなのかなと思っています。
今回演奏させていただくピアノ協奏曲第23番もまさにそうで、人の感情の動きに自然と寄り添ってくれる作品。特に第1楽章は人間の明るい部分も暗い部分も見せてくれるような音楽になっています。
 公演直前!オンライン・インタビューでの北村明日人さん 2025年9月3日
公演直前!オンライン・インタビューでの北村明日人さん 2025年9月3日2022年に特級でグランプリを受賞したときも、ベートーヴェンのピアノコンチェルトを演奏されていました。モーツァルトのピアノコンチェルトにしっかり取り組んだのも、特級を終えた後が初めてだったとのこと。改めて、特級を振り返ってみていかがですか?
僕はドイツ語圏のチューリッヒに留学していたため、ドイツの音楽がすごく好きなんですね。だから、結果がどうであれ、自分の好きな作品でピティナの特級に挑戦したいという気持ちがありました。 実際にグランプリを受賞すると、まずは責任感と怖さを覚えました。子どもの頃から見てきた特級グランプリの受賞者の皆さんは、自分にとっては憧れのお兄さんやお姉さんだったのに、自分がその立場になってしまって……。それに、改めて自分がどんなことをやっていきたいのか、言葉にしなければならない場面も多く、「今ちゃんと表明しておかないともったいない」と思っていたのも覚えています。もう、本当に怖かったですよ(笑)。
当時、北村さんは「子どもたちの伴奏をしたい」とはっきりと言葉にされていたとか
はい、そうでした。それからはさまざまな公演のたびに、たくさんの音楽をやっている子どもたちと出会い、また今では伴奏のお仕事をいただくことも多く、あのとき思い描いた夢やプランが順調に叶っていっています。
他にも、受賞から現在に至るまでに変化はありましたか?
受賞後もたくさんの本番の機会をいただくようになり、どうしても忙しくなって時間的な厳しさも出てくるようになったのですが、いい意味で一種の“諦め”ができてくるようになりましたね。自分がどれだけ悩んでいても、この作品は素晴らしいのだから、自分はその素晴らしさを伝えるだけでいいのだから……と、投げ捨てる意味ではなく、自分と作品を切り離して考えられるようになりました。
ポジティブな諦めですね。ある意味、作品と純粋な状態で向き合うことができそうです
やっぱり、学生時代はどうしても音楽と自分を一体化してしまいがちで。もちろん、しっかりと練習に取り組むことは大切ですが、過度に一生懸命になりすぎても、「その向き合い方は本当に音楽のためになっているのか?」と疑問を持てるようになったというか。それがまわりまわって、「どうせ自分ができることは、そんなにないよな」とわきまえられるようになりました(笑)。
北村さんの思う、ピアノコンチェルトの魅力を教えてください。
1人の人間が1つの作品を弾くのはごく自然のことですが、1つの作品を何十人と一緒に奏でることへのおもしろさがあると思います。
ピアノ協奏曲は華やかだと言われることが多いジャンルですが、華やかさは結果の話です。そこに至るまでに、音と音の間にある何かを探ったり、他者の音を聴いて「普通ならこう演奏するのだろうけど、こっちの方がいいな」と試してみたりして、即興性を大切にしながら音楽を作っていく。そこに自分が思いもしなかった呼吸や音色が生まれて、「人間ってこんな動きもするんだな」と思ったり、新たな流れを生み出すことができたり……。
最終的には1冊の本を読んだような達成感を生み出し、それを聴衆のみなさんと共有できるのが理想だと考えています。
本番のステージだからこそ生まれる即興性もありそうですね。
確かにそうかもしれませんが、それでも1人で演奏するときと、誰かと演奏するとき、あまりやるべきことは変わらないと思っていて。音楽における役割を1人で担うか、誰かと分け合うか、といった違いだけだと思います。
特に、僕はモーツァルトやベートーヴェンの生きた古典派時代のピアノコンチェルトが好きなのですが、それはピアノそオーケストラの役割がはっきりと分かれているわけではないからなんです。オーケストラが必ずしもピアノを引き立てる役割に収まっていないから、ピアノを弾いているソリストもオーケストラの一員になれるような気がするというか。
今回、演奏させていただくモーツァルトのピアノ協奏曲第23番も、まさにそんな作品だと思います。
最後に改めて、北村さんの思う特級グランド・コンチェルトの聴きどころを教えてください。
まったくキャラクターの異なる3つのピアノコンチェルトを楽しめるのが一番のポイントだと思います。モーツァルト、ショパン、ブラームス、それぞれの作品によって、ピアニストの役割やオーケストラの規模、音楽の特徴がまったく異なります。ピアノコンチェルトという1つのジャンルの中でさまざまなカラーのアンサンブルをお楽しみいただけるのではないでしょうか。
ちなみに、今回ご一緒させていただく桑原さんは同じ高校で1つ上の先輩でした。門下の先生も同じだったので、すごく仲良くさせていただいていました。進藤さんはまだお会いしたことはないのですが、今回を機に演奏を聴かせていただくのが楽しみですね。
ありがとうございました!
公演詳細・チケットお申込へ