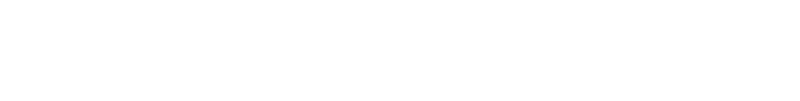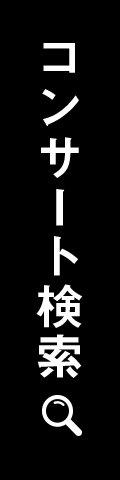特級グランド・コンチェルト直前インタビューVol.1 桑原志織さん

「ブラームス 第2番」

聞き手:加藤哲礼(ピティナ育英室長)
いよいよ9月19日にせまった「特級グランド・コンチェルト」。桑原志織さん・北村明日人さん・進藤実優さん、特級を巣立って、ザ・シンフォニーホールのステージに立つ3人に、今回演奏する作品の魅力とこのコンサートへの思いをたっぷりと語っていただきました。第1弾は、エリザベート王妃国際コンクールでの活躍も記憶に新しい桑原志織さん。ルービンシュタイン、ブゾーニ、ヴィオッティ、マリア・カナルスなど既に国際舞台での活躍も著しい実力派です。
「特級グランド・コンチェルト」ご出演ありがとうございます。今回は、5月のエリザベート王妃国際コンクールでのファイナルでも演奏されたブラームスのピアノ協奏曲第2番という大曲を演奏していただきます。この曲はどのくらい演奏しているのでしょうか。
この曲は意外と新しくて、昨年から1年ちょっと勉強して、オーケストラとは昨年の秋に1回合わせたことがあり、エリザベートが2度目でした。
演奏者にとってどんな作品ですか?
長大な曲と言われますが、弾き手になってみると「良いな~」と思う部分の連続なので、全然長くない曲だと感じます。一方で、聴いている方にとっては長い曲ですから、そこでいかに長さを感じさせないかが難しいですね。焦ったように感じさせてしまっては曲の魅力を殺してしまいますし、ただ作品の波に乗っているだけでもいけませんし。あまりそのようなコンチェルトはないですよね。ピアノ協奏曲は、おおむね30分くらいの作品が圧倒的に多いので、その枠から出ると、とたんに「長いな」と感じてしまうと思うのです。その<長さ>にどう向き合うかが難しいところですね。

1年以上勉強してみて、協奏曲第2番の魅力はどのあたりにありますか?
一言で言うのは難しいです。ブラームスは作品120番台まで書いていますから、多作の作曲家で、初期・中期・後期、本当に作風が変化していった人だと思うのですが、この2番のコンチェルトには、第3楽章のように室内楽的な、そして後期寄りの雰囲気を感じさせるところもありながら、完全に「精神世界」みたいなところには行ききらず、若い頃のピアニスティックな魅力も充分に残っていますし、そうした<過渡期>ならではのミックスされた魅力、変化していく瞬間だけが持つ魅力があって、色々な好みの方に受け入れていただきやすい要素を持っているのではないでしょうか。ブラームスの様々な魅力、ブラームスの人生がちょうど1曲の中で混ざり合っていて、「よくぞ、この時期にこの曲を残してくれた!」と思うような独特の魅力がある作品だと感じます。そういう魅力を持った曲って、他の作曲家でも、意外と少ないように思います。この魅力は「コンチェルト」だから出せたというのもあるかもしれません。ソロの曲だったり、逆にシンフォニーだったりで、そこに色々なキャラクターを含んでいるなと思う作品は多くないですが、「オーケストラ」と「ピアノ」という、ある意味で本来相容れない要素を持つものが、ピアノという楽器の音量や可能性がとても大きいために、オーケストラと一緒になったときに、対峙したり相乗効果が出せたり、それぞれがマーブル模様にミックスした「ピアノコンチェルト」独特の魅力になっていて、これは、このブラームスのピアノ協奏曲第2番ならではの聴きどころだと思います。
ブラームスという作曲家についてはいかがですか?
昨年、ピアノソナタ第1番(Op.1)を弾いて、留学した初期のころには、後期のOp.118や119を勉強しました。その両極の作品を勉強したというのが、ピアノコンチェルトを弾くときにも大切な過程になっていると思います。作曲家の作品の一番最初と最後がピアノで弾ける作品だというのは、幸せなことです。実は、留学する前は、ブラームスは私にとってはあまり馴染めないというか、理解しづらいところのある作曲家でした。室内楽を弾く機会は多くいただいて、それは楽しかったんですが、自発的に取り組みたいなというほどではなかったんです。ただ、留学して、色々な方のブラームスの演奏に触れて、いいなと思うことが少しずつ増えていきました。最初から大好きだったわけではなく、むしろ「ちょっとよく分からないな」と思っていた部分が少しずつ分かって魅力的になっていったからこその感じ方があります。そこは、ベートーヴェンやラフマニノフのように初めから好きだった作曲家の作品を弾くとき以上に、練習していてどんどん自分の中で変化していく感覚があるんです。最初から好きな作曲家は、「こう弾きたい」というのがあるので、そこはあまり変わっていかないことが多いのですが、ブラームスに関しては、自分の中でも紆余曲折してきた作曲家なだけに、ある意味で「いまだに毎回新鮮」で、それはこのコンチェルトにも言えることですね。今回も、初めて演奏したときとも、エリザベートのときともまったく別の演奏になるだろうと思います。
 5月、エリザベート王妃国際コンクールピアノ部門ファイナルにて
5月、エリザベート王妃国際コンクールピアノ部門ファイナルにて 藤岡マエストロと関西フィルの皆さんとのブラームスは、どんなふうになりそうですか?
以前、同じ「特級グランド・コンチェルト」シリーズでシューマンを演奏させていただいたのが初共演でした。藤岡先生と関西フィルの皆さんは、マエストロとオケの間のつながりがすでにものすごく濃くて親密なので、その親密さから来る音楽の土台がしっかりしている感じがします。私は、その輪の中に入らせていただきつつ、信頼できる土台の上で、かなり自由にやらせていただいて、一体感を感じさせていただいたり助けていただいたりしました。
今回のブラームスは、シューマン以上にシンフォニーの要素が強いですから、マエストロとオケの強い信頼感がよりいっそう生きて、私もその中でこれまでと違う全くフレッシュな感覚で弾けると思います。エリザベートでの演奏はYouTubeでまだ聴けますが、そのときとは絶対に全然違う演奏になると思いますので、来てくださる皆様にそこを楽しんでいただきたいですね。奏者の組み合わせが変わったらまったく異なる演奏になるというのが、音楽の魅力のひとつですし、私自身もお客様と同じように楽しみにしています。
「特級グランド・コンチェルト」は他のお二人のピアニストとの演奏になります。この点はいかがですか?
私は一度「グランドコンチェルト」に出させていただいていて、そのときは谷昂登さん・阪田知樹さんとご一緒しました。阪田さんは、もともと仲の良い先輩ですが、同世代の方々と、コンクール以外で並んで演奏するということはなかなかない機会なので、楽しかったです。コンクールという場では「他の人の演奏に左右されないようにしなければ」と思ってしまいますが、コンチェルトのガラコンサートでご一緒して、例えばリハーサルやゲネプロを少し聞かせていただいたり、隣から練習が聞こえてきたり、そんなことも楽しくて、出演する側にとってもちょっとお祭りっぽいところがありました。室内楽で他の楽器の方々と一緒にというのはあっても、ピアニストどうしで一緒の時間を作っていくというのは珍しく、とても楽しい時間でした。今回は、進藤実優さん・北村明日人さんとご一緒します。北村さんは高校時代から同門の後輩で面識があって、人柄も演奏も素晴らしいのは昔からよく知っています。今回、久しぶりの再会で(とは言っても、一方的に演奏を聴かれていたことはよくあるんですが!)楽しみにしています。進藤さんは、学年も少し離れているので、たぶんほとんどお会いしたことがなくて、ほぼ初対面みたいな形ですが、素晴らしい個性を持ったピアニストだということはもちろん存じ上げています。今のところ動画の演奏の中でしか知らない進藤さんの、演奏だけではない人となりを知ることができるのもすごく楽しみです。同世代の優秀なピアニストたちと交流して、影響を受け合って、また音楽を深めていけるというのがとても楽しみな機会ですし、そういうコンサートはやはりピティナという組織ならではだなと思います。ぜひ、聴いていただく皆様にも一緒になってこの「お祭り」を楽しんでいただきたいです。
9月19日のブラームスを楽しみにしています!ありがとうございました。
公演詳細・チケットお申込へ