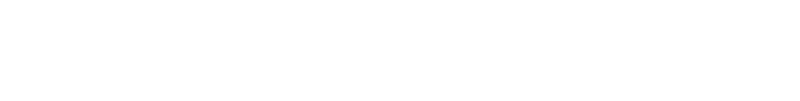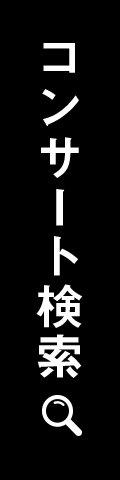特級グランド・コンチェルト直前インタビューVol.3 進藤実優さん

「ショパン第1番」

聞き手:桒田萌(ライター)
今回演奏されるショパンのピアノ協奏曲第1番は、2021年に銀賞を受賞された特級のファイナルで演奏されていましたね。
はい。当時は、およそ1ヶ月半後にショパン国際コンクール(セミファイナルに進出)を控えていて、特級でもショパンを多く演奏していました。ピアノ協奏曲第1番を含め、今はショパンの作品を前よりもリラックスして臨めているように思います。今年10月に開催されるショパン国際ピアノコンクールにも出場する予定なので、今はもう一度楽譜を読み込んで、以前は忘れておろそかになってしまいがちだった細かな部分を再度確認しているところです。
ショパンは私の中で最もレパートリーの多い作曲家で、それもあってか、どこか感情移入してしまう存在でもあります。舞踊の要素とメロディックで抒情的な歌の要素。この2つが重なった素敵な作品が多く、弾き手としても感情が入ってしまうというか。
そのため、演奏する際は自分の直感のままに弾きつつ、同時に客観的な視点で一歩引くようにして、自分の感情が優位にならず音楽そのものを伝えられるように意識しています。
改めて、ショパンのピアノ協奏曲第1番について教えてください。
ショパンが20歳と若い頃に作曲しているため、エネルギーに満ち溢れた作品です。たとえば第1楽章は、感傷的な一面もあるのですが、まだ若いということもあり、過去を振り返る切なさよりも、その瞬間に覚えた感傷を表現しているような印象があります。また、先ほども舞踊の要素があると言ったように、第3楽章はクラコヴィアクというポーランド特有のダンスで書かれているのも特徴だと思います。
2021年演奏されたときと現在では、ショパンのピアノ協奏曲第1番への取り組み方にどんな変化がありましたか?
以前は一音一音に熱や芯を込めるタイプだったのですが、今はもう少し全体を俯瞰しながら演奏できるようになったように思います。ピアノ協奏曲第1番の場合、全体の構成や、第3楽章の民族的な要素にも目を向けられるようになりましたね。
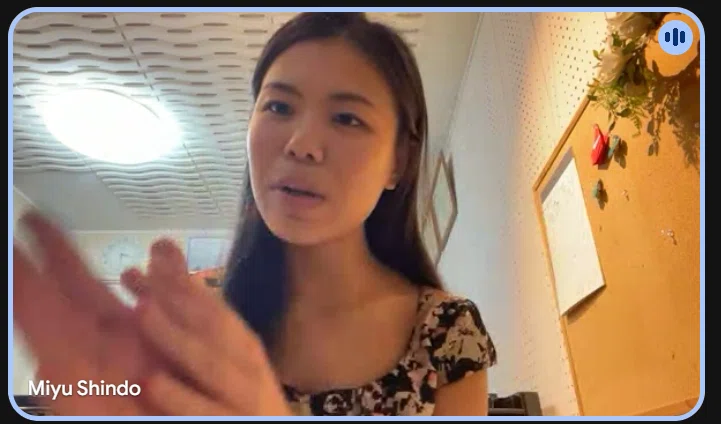 オンラインインタビューでの進藤実優さん 2025年9月5日
オンラインインタビューでの進藤実優さん 2025年9月5日特に当時は、特級とショパン国際ピアノコンクールへの出場が重なり、とてもハードな1年だったのではないかと思います。
そうですね。特級は国際コンクールさながらいくつもステージがあり、その度に多くのレパートリーが要されるため、ショパン国際ピアノコンクールを控えている私としては試される思いでしたし、とても充実した時間でした。
当時の私は、自分の頭の中で聴こえている演奏と、実際に響いている演奏にギャップがあるという課題がありました。自分の中に、「こう弾きたい」という確固たる思いがあり、そこからそれてしまうと「だめだったな」と思ってしまう。一音一音の音色に執着するタイプであることもあり、「この音が欲しい」と思ったら、体がこわばったり、極端に力が入ったりする癖もありました。特級の2次審査では、そのギャップもあってか、「全然うまくいかなかった」と落ち込み、舞台裏で泣いていたくらいです。
今はそれが改善されて、力を入れるときは入れて、抜くときは抜く、といった力配分を考えられるようになりました。これはショパンを演奏するときにも欠かせない工夫だと思います。
ピティナ特級と前回のショパン国際ピアノコンクールを終えた2022年よりドイツのハノーファー音楽演劇大学に留学されていますね。そういった変化に、ドイツでの学びは影響がありますか?
ドイツでついている師匠の影響が大きいですね。音楽家と教育者、2つの立場からさまざまなアドバイスをいただいていて、日々学びになっています。
ピアノに関する技術の指導についてはもちろんですが、作品に取り組む中で、「どうしてこう表現したいのか」「どうしてこんな演奏にする必要があるのか」といった原点に立ち返る問いを与えてくださるんです。日々、音楽について深く考察する時間が増えました。
それに伴って、演奏の組み立て方も変わりました。作品に取り掛かるときは、まずはすでに残されている音源を聴きながら、「この演奏家の解釈は素敵だな」と参考にして音楽を作っていたのですが、今では「まずは自分がどうしたいのか」を考えるようになりましたね。

進藤さんの思う、ピアノコンチェルトの魅力を教えてください。
1人による演奏とは比べものにならないくらいの音の迫り具合。あと、終盤特有の高揚感は、決して演奏者1人では出せないものだと思います。
進藤さんがピアノコンチェルトを演奏されるときに意識されていることはありますか?
ピアノコンチェルトでは、時にソリストがオーケストラを引っ張っていく必要もあるため、自分のテンポを見失わないようにしたり、オーケストラ内の楽器との掛け合いを大切にしたり、といったことを意識しています。
テンポの維持については、練習時にも対策していて。取り組んでいる作品の音源を大音量で流して、そこに自分のピアノを重ねて演奏する、といった方法です。そうすることで、自分のテンポやルバートの癖が発見できるんです。

進藤さんの思う特級グランド・コンチェルトの聴きどころを教えてください。
北村明日人さんと桑原志織さんにはお会いしたことがないのですが、すでに聴かせていただいたことはあって、素敵な演奏をされる印象なので、同じ舞台に立てることが何よりうれしいです。モーツァルト、ショパン、ブラームス、音楽的に幅広い3つの作品と、三者三様の音楽づくりで、違いをお客様にも楽しんでいただけると思います。
この公演を終えた後の展望を教えてください。
まずは10月にショパン国際ピアノコンクールを控えているため、こうして特級グランド・コンチェルトでピアノ協奏曲第1番を弾けることが大変ありがたいと思っています。
まずはコンクールに励み、その後はいろんな国や場所で演奏して、たくさんの方に聴いていただきたいですね。そして、ゆくゆくは演奏だけでなくプラスでおもしろいと思える要素のあるコンサートができたらと思っています。一貫したテーマ性やメッセージ性があったり、お客様が音楽の世界観に浸れたりするようなプログラムを組みたいですね。

企画の切り口やメッセージ、テーマを考えるのは知的な営みでもありますよね。普段はどんなふうにインプットや勉強をされているのでしょうか?
音楽に関する本を読むのはすごく好きです。あとは、歌舞伎などの日本の伝統芸能にも興味があって。西洋のクラシックとの違いを知ったり、その上で双方の文化の本質の差異や共通点を感じ取ったりするのが楽しいです。そんなインプットの積み重ねで、自分のやりたいことや活動の切り口を見つけていきたいなと。まずはこの特級グランド・コンチェルトを楽しんで、さらに自分の演奏を高めていけたらと思います。
 インタビュアーの桒田萌さんと、進藤実優さん(右)
インタビュアーの桒田萌さんと、進藤実優さん(右)ありがとうございました!
公演詳細・チケットお申込へ