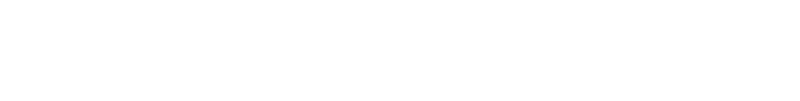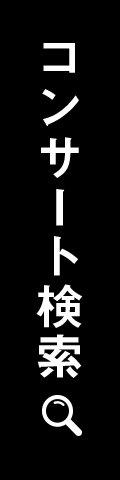開催レポ:スタインウェイ特級スペシャルコンサート
会場:スタインウェイ&サンズ東京
出演:嘉屋翔太(p)、神原雅治(p)、三井柚乃(p)、鈴木愛美(p)
主催:スタインウェイ&サンズ東京
後援:一般社団法人 全日本ピアノ指導者協会(ピティナ)
写真撮影:山平昌子
第47回ピティナピアノコンペティション、特級入賞者4人によるコンサート。4人のファイナリストの演奏を一度に聴けるのは、この夏のサントリーホールでのファイナルステージ以来です。この半年の間に、ファイナリストたちはどんな変化を遂げたのでしょう。特級の各ステージを思い出しながら、イルミネーションの輝く表参道を抜け、会場となったスタインウェイ&サンズ東京に向かいました。
何台もの輝くピアノと、クリスマスツリー。ラグジュアリーな邸宅にお邪魔したようなくつろいだ雰囲気です。ポリーニやツィメルマン、内田光子など世界的なアーティストに見守られたスタイリッシュなサロンでは、30名ほどのお客さんが開演を心待ちにしていました。

最初にステージに現れた嘉屋翔太さん。堂々とした立ち居振る舞いに、数多くのステージを踏んできた自信を感じさせます。特級のステージでもそうだったように、嘉屋さんのプログラミングにはいつも、聴き手を日常から音楽への自然に誘導する、巧みで効果的な仕組みが用意されています。この日も、街の喧騒と地続きのように自然に、ゴンドラは水面に滑り出しました。不穏な響きの中に、穏やかな景色や回想を思わせる音色が挟み込まれます。波のように行きつ戻りつするフレーズに身を任せるうち、次第にそのうねりは大きくなり、あらがえない運命の如く会場を飲み込んだあと、潮が引くように去っていきました。
続く「J.S.バッハ=ブゾーニ 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番ニ短調BWV1004より シャコンヌ」。先ほどの艶やかで伸びやかな響きから、木と石を想起させる乾いた手触りへ、音色ががらっと変わります。大聖堂を響かせる讃美歌、神にだけ捧げる独白、届かぬ場所にいる大切な人を思って風に乗せる祈り。荘厳な響きの中に、スライドショーのように目まぐるしく異なるイメージが差し込まれました。それらはメロディーと和声で表現される異なる情景のようでありながら、実はただ一つの祈りの言葉なのかも知れません。やがてすべてが救いの光に溶け込むように、15分近くのドラマが幕を閉じました。
「死」を意識してプログラムを組んだという嘉屋さん。ワーグナーの死を意識して書いたと言われるリストと、生々しく描いた生によってより「死」が色濃く際立つようなバッハ。異なるアプローチで「死」を描いた2曲のプログラムに、会場は納得するかのような感嘆のため息に包まれました。

ステージに静かに現れたのは神原雅治さん。シューマンのアラベスクop.18が始まりました。温かく繊細な音色は、小動物を撫でた時に指に伝わってくる、かすかで確かなぬくもりのようです。大聖堂を思わせる嘉屋さんの風景から、急に別の小部屋に映ったような展開に、心地良い刺激を感じながら耳を傾けました。くぐもった光のような音色に、ふとフェルメールの絵画「手紙を読む女」を思い出しました。とすれば、この複雑に絡み合う音型は、手紙の中の文字の連なりか、彼女が着るドレスの刺繍でしょうか。あるいは手紙の相手との絡み合う心情や状況かも知れません。
続くブラームス「4つの小品op.119」。穏やかなフレーズが、孤独な回想のように浮かんでは消えていきます。この曲で描かれる感情は、喜びも苦悩も、薄い膜がかかったように現実味が感じられません。でもそのメロディーを遠くから眺めてみると、雪原に描かれたシュプールのように、不規則な軌跡が浮かびあがって来ます。最晩年に作られたというこの3つの間奏曲の中で、ブラームスは気ままに思い出を辿っていたのでしょうか。4つの小品のうち、ひとつだけ「狂詩曲」と名付けられた最終曲は、それまでの曲調と一転して、濃密で、現実的な感情が感じられます。人生の感傷的な回想に冷や水を掛けるような現実的な苦悩、人生の理不尽さを神に問いかけるようなむき出しの感情で、曲は締めくくられました。あの穏やかな始まりから、いつの間にこんなにも濃密で率直な表現に至ったのでしょう。穏やかさと繊細さから、狂おしさと熱情へ。知らぬ間にキャラクターが入れ替わる、ある種裏切られたようなその印象に、この夏のセミファイナルでの、神原さんの鮮烈な「クライスレリアーナ」を思い出しました。

休憩後、三井柚乃さんが少し緊張した面持ちで舞台に向かいました。三井さんの一貫した愛と尊敬の対象である、シューマン。この夏、特級の各ステージを通じても、その想いを表現してくれました。選んだのは「子供の情景 OP.15」。
水を思わせる澄んだ音色は三井さん独自のもの。いつもながら、「同じピアノなのにどうしてここまで音が変わるのだろう」と不思議に感じます。事前のインタビューでは、「子どもの情景」と名付けられたこの曲は、子どものための教則本ではなく、大人の目線で見た子どもの世界を表現しているのだと教えてくださいました。「見知らぬ国から」「おねだり」など、愛らしい名前が付けられたそれぞれ1~2分の曲を聴くことは、絵本の読み聞かせに身をゆだねることに似ています。ページをめくるごとに、くるくると表情が変わる曲調は、無邪気で自由な子どもの日常そのもの。時折差し込まれる落ち着いた声色は、物語の語り部でしょうか。この曲に登場する人物のキャラクターや台詞を、三井さん独自の感性で解釈し、丁寧に表現していくことで、物語は深みと説得力を持って進みます。有名な「トロイメライ」に差し掛かると、気づかないうちに緊張していた心と身体が優しく解きほぐされるようでした。
インタビューでは、表現者として、自分という存在自体を磨きたい、とおっしゃっていた三井さん。音楽に限らず他の分野からも学びたいとおっしゃっていました。そうした意識が、この日の広がりを持った物語づくりにつながったのでしょう。

シューベルト「楽興の時D780 OP.94」を選んだ鈴木さん。牧歌的なモチーフの繰り返しは、シューベルトの自問自答のよう。事前インタビューの中で鈴木さんが一番好きとお話してくださった第2番では、冒頭の柔らかな和音を構成する音のひとつひとつが、大切なメッセージを語る肉声のようでした。音数の少ないメロディーとシンプルな伴奏の中に、今の私たちにも共通する喜びや苦悩が感じられます。シューベルトの生きた200年前の時日常と今。技術や暮らしが大きく変わったように見えて、人の営みは大きくは変わらないのだと感慨を覚えました。
シューベルトの楽曲の、特にこうした小品からは、聴衆の存在や音楽的な野心があまり感じられません。見られることを想定していない、日記に綴られた個人的な感情や日常を垣間見ているようです。そして同様に、この日の鈴木さんの演奏も、ピアニストが聴き手に楽曲の解釈を届けるというよりも、鈴木さんと同じ目線で、曲の深淵に目を凝らし、探求するような時間でした。
先の3人のピアニストが、それぞれ現段階の解釈と応えを伝えようとしてくれたのに対し、鈴木さんはこの曲の深みと、そこに到達するための問いかけを共有してくれたのかも知れません。すっきり割り切れる後味を与えないことで、かえって聴衆のこの曲への興味を持続させる、そんな演奏だと感じました。私の手の中には、今も鈴木さんが共有してくれた問いがあり、まだその手触りを吟味しています。特級のステージにおいても、鈴木さんの演奏の後味は、いつも数日間、私の心に漂っていたことを思い出しました。

久しぶりに集った4人のファイナリスト達は、季節ふたつ分の短い期間に、それぞれの道を着実に進んでいるようです。ひとくくりに「ピアニスト」と言っても、それぞれの目指す道が驚くほど異なることを改めて感じました。そうした視点で改めて振り返ると、特級での経験はそれぞれのファイナリストが自らの強みや弱みを明らかにし、表現者として追求すべき道をより明確に照らすための重要な機会だったのでしょう。
この日のプログラムもドイツの作曲家が中心でしたが、2024年2月24日には、ファイナリスト4人によるオールブラームスのプログラム「一輪の薔薇が咲いて」が、J:COM浦安音楽ホールコンサートホールにて開催予定です。さらに成長と進化を遂げたファイナリスト達の競演を、ぜひ現地で味わってください。

レポート◎山平昌子