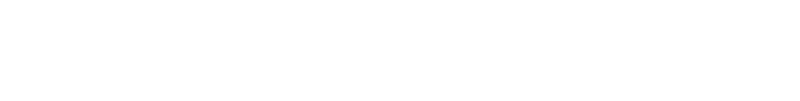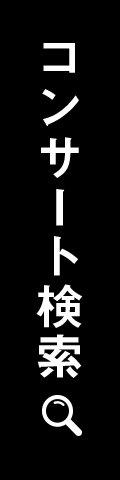50周年企画「対談インタビュー」 第4回 若手指導者による座談会


連載第4回は、指導・審査アドバイス・演奏などで活躍する30-40代のピアニストにお集まりいただき、日々の音楽活動や指導の中で感じることを自由にお話しいただきました。常に次の時代を取り込み、人材もアイデアもアップデートしてきたピティナ。未来を担う新たな世代の指導者たちは何を感じているのでしょうか。
◆ 聞き手・進行:加藤哲礼(ピティナ本部事務局長)
今回は座談会形式ということで、各方面でご活躍の30-40代の方々にお集まりいただきました。ピティナ創立者の福田靖子先生も、創立時は30代半ば。ちょうど我々の世代で音楽教育の未来像というのを考えていたことになります。まず、先生方それぞれのピティナとの関わりを伺えますか?

- 加藤真
-
デュオを組んで2,3年目、2001年にデュオ特級でコンペに参加したのが最初でした。4年半ドイツに留学して帰国した後、課題曲CDの演奏にお声がけいただき、江崎光世先生やスタッフの方とお会いしたのがきっかけですね。
- 高木
-
私は、第15回(1991年)のピティナG級を初めて受けて、全国大会は大好きなカザルスホールで弾かせていただきました。2000年にCD収録に声をかけていただき、そこから審査や演奏などでお仕事をさせていただくようになりました。
- 大嶺
-
私は、小6で初めて受けたコンクールがピティナでした。当時の沖縄本島には、コンペの予選がなかったので、飛行機で宮古島へわたって参加しました。そのご縁で、アメリカのジーナ・バックアウアーコンクール見学&コンサートツアーでは福田靖子先生とご一緒しましたし、2000年に若い音楽家のためのルービンシュタイン国際で1位だったときに、「福田靖子賞」をいただいたご縁があります。
帰国してから、審査や演奏などで関わらせていただいています。
- 山崎
-
僕はパートナーの濱本愛がG級で金賞に入り、各地の入賞者演奏会に呼ばれているのを見て、すごく大きな組織だなと思っていたのが最初です。その後、二人でデュオを組むことになって、デュオ特級を受け、1位をいただきました。ひょっとしたら、特級も受けていたのかな? 数年後に、連弾でお仕事をいただき、今は、課題曲説明会や録音、審査・アドバイスなどをさせていただくようになっています。
音楽に目覚めたきっかけ、原体験は?
- 高木
-
私は聴くほうから入りました。自宅で流れていたアラウのチャイコフスキーが原体験で、LPの針飛びまで憶えています。学生時代は、お小遣いをCDとコンサートにつぎ込み、友達とポリーニの「出待ち」をしたのも青春の思い出。クラス内で、いつも音楽が共通の話題でしたね。
- 山崎
-
ホント?僕は普通高校だったので、音大へ行けば音楽の話ができるかと思っていたら、実際はそうでもなかったです(笑)。昔は、それこそ「すり切れるまで聴く」という言葉があったけど、今はYouTubeもクリックひとつ。1分も聞かずに「これは気に入らない」という時代ですね...。
- 加藤真
-

母が音楽好きだったので家に音楽は流れていたけれど、こちらはシューベルトとシューマンの区別も付かないくらいで・・それが、音楽高校に入って少しずつ情報の欠片がたまってきて、ある日それが器から溢れるような瞬間があった。僕の場合は、18歳くらいで聴いたマーラーの交響曲がきっかけとなって、そこから周囲の作曲家に広がっていって、徐々に自分なりの<音楽史>ができてきたら、どんどん楽しくなってきた。そのあたりからようやく音楽に能動的になってきた気がしますね。だから「何も知らない」とか、いまの学生たちに偉そうなことは言えません。
その「楽しさ」は、たとえば指導者が与えてあげられるものでしょうか。指導者はどういうものを生徒に与えてあげられるでしょうか。振り返ってみていかがですか?
- 加藤真
-
細かい要素よりはむしろ、先生方ご自身の「生き方」に影響を受けていると思います。先生がこちらを向いてやってくださったことだけではなく、「背中で見せて」くださったことが大きかった。
- 高木
-
指導者自身が楽しんで、自分の世界のフィールドを持っているというのは、大きいよね。
- 大嶺
-

そう。私の先生は、「シューベルト弾き」の辛島輝治先生、ショパンを追求しているパレチニ先生や下田幸二先生、ロシア物とコレペティの技術に定評があったラピツカヤ先生と、皆さん、ご自分の軸を持った方でした。私も、ラフマニノフ全曲演奏を行ったときに、「もっと色々なものを」という声もあったけれど、そういう先生方の背中を見てきたので、あまり気になりませんでした。
- 高木
-
私も、習ってきた先生方全員が、教えながら演奏を追求していらっしゃった。学生の頃は分からなかったけれど、指導の仕事や家庭や、様々なものを持ちながらピアノを弾き続けていくのがどれほどのことか、今になって分かります。そういう姿を見て、私自身も、人前で弾くということを1日でも長くやっていきたいし、新しい作品をイキイキと子供みたいに楽しそうに勉強していた自分の先生方のようになりたい、と思います。
- 加藤真
-
某大学の合同発表会で、自分の生徒たちのソロが下手すぎてがっくりしたのですが(笑)、でも、最後に弾いた連弾はとても上手で、これはひょっとして、ソロとしての背中を見せられていない自分のせいかもしれないと(笑)。
- 山崎
-
実際、デュオのほうが個性が出やすい、というのは、あるよね。
- 加藤真
-
そう。やっぱり、デュオのほうが精神的にも情報量的にも少しだけ「楽」なんだよね。ソロは1人で処理すべき情報が多すぎて本当に大変。デュオで、1人あたりの情報量を少し減らして音楽に向かうのは、とても良い経験だと思う。
- 山崎
-
僕も、連弾をやっているときのほうが、音楽全体を見渡して指揮者の気分を味わえることがある。その経験は指導にも生きていて、ソロとは違う視点で音楽を見るという力を伸ばすことができました。
- 加藤真
-
だから、僕たちの結論は、デュオをやったらいい、と(笑)。偏見かもしれないけれど、他の専攻生に比べてピアノ科の学生は、音楽が少しだけ幼稚と思うことがある。というより、求められることが多い。例えば旋律楽器だとひとつの音に集中できるところで、ピアノは1人でたくさんの要素を弾かなくてはいけないから、大変なのだろうなと。
- 高木
-

まさにそこで、いつも悩みます。ピアノって、「本来の楽しさ・面白さ」に行く前に、小さい頃にトレーニングしてあげなければならない基本的なことがすごく多くて、特に、あるレベル以上を目指そうとする子には、自分の意志や個性が出るまでに上手につなげてあげたいのだけれど、それが今はとても難しく感じています。トレーニングした成果を「使って」創造していくところが、人間として一番ワクワクするところなんだけど...。そのあたり、皆さん、どのように指導しているの?
- 全員
-
・・・そう。難しいよね。
- 山崎
-
生徒によって返ってくる量が違うから、どのくらい返してくるかで、こちらの対応も変わるし...。それが突然「音楽の道に行きたい」と言われたときには、さらに難しい。背景にある文学とか歴史とか、そういう話もしてあげたいけど、それ以外にレッスンの中で扱うことが多すぎて、特に本番が近いと、なかなか話してあげられないなぁ。
- 高木
-
私はむしろ、しゃべりだしたら止まらなくなって、生徒は「そんなのいいから早く弾き方を教えてよ!」という目で見てくるんだけど、でも話が止まらない(笑)。
- 加藤真
-
きっと、ずーっと後になって、その話の意味が分かることもあるのでは?
- 高木
-
特にピアノやヴァイオリンは、基礎的なことの習得が子どもたちに早い時期に求められる。スポーツも同じだけれど、でも芸術は長い。人間としての成長と、子ども時代のトレーニングをどうやって組み合わせていけばよいのか・・。大嶺さんはどうだった?
- 大嶺
-
小さい頃の私は、苦しい思い出の方が多かった。弾いても弾いても自分が思うものに至らなくて。「上手になればもっと素敵な曲が弾ける」「国際コンクールでファイナルまで残ればコンチェルトが弾けるかもしれない」そういう一心だったかな。でも、「やっぱりやりたい」という思いがどこかにあったから、続けたんだと思う。
- 山崎
-

ある程度、結果を出している子は続けられるし、コンクールで失敗してばかりいると、自信を失ってやめてしまう、という世界がある一方で、コンクールを知らずにずっと続けて長く楽しんでいる方をステップで聞かせていただいたりもしますね。コンクールばかりを受けていると、どうしても平均的な演奏になりやすい、というのはあるのかなと思います。
- 大嶺
-
その点、留学して驚いたけど、ポーランドの人は、結果を全く気にしないんですよ。審査員に何を言われても全然平気。自分の個性に確信を持っている子が多いです。私が、本番の後に「ダメだった、最悪だった」と言うと、「何があったの?病気なの?」って、結果のことじゃなくて体調の心配をされていました(笑)。
- 山崎
-
個性、個性という時代だけれど、演奏は似たり寄ったりになってきているようにも思うけれど...。どうですか?
- 加藤哲
-

うーん。そうかもしれないけれど、そうではないかもしれない。特に子どもたち・若い人たちの演奏は未熟で発展途上なわけだから、個性の差異や発現も小さいはずで、単に「聴く側がその微量の差異を聴き取れていないだけ」という可能性は捨てきれないと思う。「弾く力」「教える力」に比べて、「聴く力」の測定はずっと遅れているから、表面化しないだけで。
だから、コンクールの結果も、半分は弾き手の力。半分は聴き手の力。さっきの大嶺さんの話でも、ポーランドの人たちは、直感的に、そこで出される結果には何の根拠もないってことを、分かっているんじゃないかなと思います。
- 高木
-
これだけコンクールがあって、情報が溢れて、皆が「正しい答え」を探している時代に、そういう見方を知っていると、コンクールの捉え方も変わるかもしれないよね。
人工知能(AI)の時代が来て、いつか、正確に、完璧なバランスで楽器を弾くのは機械がやってくれるかもしれない。けれど、私たち人間には、直感とか想像力とか経験とか、色々な情報がその人なりに結びついて出てくる思いがけないものとか、そういう能力がある。「音楽」って、そういう要素がとても多いものだから、まだまだ可能性はあると思う。
- 加藤真
-
最強の囲碁AIに名だたるプロが挑んでどんどん負けて、でも、これを人類の恥だ、とか思わないで、なんだかみんな盛り上がって楽しそうという状況があるんですね。AIが、自分たち人間には思いつかないようなアイデアを見せてくれたことに興奮して、「自分もまだまだ強くなれる!」とワクワクしている。それって素晴らしいことだな、と。結局のところ、自分が演奏したり音符を描いたり、「音楽をする楽しみ」「自分が向上する楽しみ」を持てるかどうかだと思います。
- 高木
-
そう、音楽の「楽しさ」を見つけてほしいよね。例えば言葉。クラシック音楽を勉強していれば、英語、フランス語、イタリア語、ロシア語...と広がっていくし、歴史・物理・数学、全部につながっていける。その広がりの可能性を、子どもたちが日々の練習で音に埋もれてしまうなかでも、伝えてあげたいです。

- 大嶺
-
ヨーロッパの人たちは自然と、音楽の背景にある歴史や文脈を知っています。でも私たちは持っていない。そこを学校のカリキュラムやレッスンでどう埋めるかは、真剣に考えないといけない。
- 高木
-
学生時代、西原稔先生の音楽思想史の授業を食い入るように聞いたなぁ。ああいう音楽史のプロの先生が教えてくださる世界史の授業とかがあってもよいかも。あと、ミッション系の学校に行っている生徒にとっては、キリストやバッハの「祈り」がよりずっと身近だったりします。大昔の「偉い人」ではなくて、その曲と自分の体験とがリンクして共感していく、そういうことを、子供の頃から、もっとみんなでやっていくべきなのかもしれません。
- 加藤哲
-
ただでさえ、バッハやベートーヴェンとは、距離が離れているし、時間もどんどん離れていくし、宗教も死生観も異なっているし、音楽を「自分ごと」にする要素が減っていくのが自然です。どうそれに抗うか。
- 加藤真
-
僕自身、クラシック音楽がこの日本で生まれたものではなく、明治期に急に海外から移植されてきて、時間的・距離的に遠いという問題は、ずっと頭から離れなかったし、それが「自分ごと」になるには、すごく時間がかかった。
- 高木
-
でも、そこが神秘的というか、なんか昔のニオイがしてきて、古本屋さんにいく快楽みたいなものはあるよね。
- 加藤真
-
僕も結局それが好きなんですけどね(笑)。その意味では、「楽譜」が中立だというのは拠り所ですね。誰が読んでも、その読み取り方のぶんだけメッセージがあるから。
- 大嶺
-
私は、最近の子供たちは、考える力、イマジネーションが弱くなったんじゃないか、と思うことがあります。インターネットで簡単に検索できて、答えを見つけたり、別の先生に乗り換えたり。とにかく何でも簡単。
でも、一人の先生を信頼して付いていくというのは「伝統をつなぐもの」としての覚悟じゃないですか。先生が、そのまた前の先生から受け継いできたスタイルがあって、それを学びに来ているはずなのに、うわべの都合の良いところだけ取って、全部学んだつもりになってどこかへ行っちゃう...。でも本当は、その「伝統」の重みを分かっていることこそが、本当の芸術家になれるか、音楽を「自分ごと」にできるかの違いだと思います。
最後に、これからの抱負を一言ずつお願いします
- 高木
-
今、指導の面白さがようやく分かってきて、若い人たちの伴走者として一緒に走ることが楽しいと思えてきています。「誰がなんと言おうと、私はこうありたい」という自我が育ってくるまで、子どもたちにとって『安心して絶望できる場所』(これ、感動した本の一節にあった言葉なんですが)でありたいですね。ピアノの先生って、親の次に生徒と一緒に過ごす時間が長いような仕事だから。
- 山崎
-
20代までは勉強して実技を磨き、30代で指導を軌道に乗せてきた。もうすぐ40歳。ある程度「型」ができたけれど、生徒を見て、改めて自分の勉強不足を感じることがたくさんあります。もっと勉強して、良い指導を続けていきたいです。
- 大嶺
-
私はもともと「演奏家」というより「教育者」に憧れていました。歴史や文化を伝える仕事ですから。
でも、弾き続けることで、生徒たちが「先生みたいに」と言ってくれることが、自分の励みにもなって、今は演奏面でももっと頑張って背中を見せなきゃと思う。自分たちを踏み台にして、いつか日本から素晴らしいピアニストがどんどん生まれたらいいなと思います。
- 加藤真
-
僕は、まだあまり「教える」というところにどっぷりつかりたくない、という気持ちもあるんです。演奏にしても作曲にしても、まだ僕自身どうしようもないレベルなので...。教えていると、生徒に「あれをしろ、これをするな」しか言ってない時があるんですが、そういうときは大抵、自分自身が演奏や作曲をサボっている。自分自身が音楽家として、舞台袖で震えたり、真っ白な五線紙の前で自分の才能のなさを呪ったりする経験が大切で、教えることはそういったものの「おすそ分け」。同じ音楽家として、生徒ひとりひとりの人間と謙虚に向かい合いたいと思っています。